|
| 楊三郎(日本時代の名前:楊佐三郎 SASABURO YO) |
|
|
 |
| 1907 |
台北市網溪(現・新北市永和区)父楊仲佐(永和市初代市長)母曾淑人(李登輝閣下夫人の叔母にあたる)の第三子として生まれる。 |
| 1923 |
基隆から商船「稲葉丸」で日本へ留学。 |
| 1924 |
京都の関西美術院に入学し、黑田重太郎と田中善之助に師事。 |
| 1927 |
作品《復活節時候》で第一回台湾美術展覧会(台展)に入選。 |
| 1928 |
作品《靜物》で第二回台展に入選。 |
|
第六回日本春陽展に入選。 |
|
陳澄波、陳植棋などの14人と「赤島社」を成立。 |
| 1929 |
関西美術院から卒業して帰国。 |
|
作品《靜物》が第三回台展で特選を取る。 |
|
作品《台灣風景》で日本全関西美展に入選。 |
|
作品《村之入口》、《滿洲風景》で第七回日本春陽展に入選。 |
| 1930 |
作品《靜物》で第四回台展に入選。 |
|
|
作品《南支鄉社》で第八回日本春陽展に入選。 |
|
| 1931 |
作品《婦人像》が第三回赤島社展に参加。 |
|
|
作品《廈門風景》、《福州郊外》で第九回日本春陽展に入選。 |
|
| 1932 |
画家劉啓祥と一緒にパリへ学習に行く。 |
|
|
作品《塞納河》でフランスの秋サロンに入選。 |
|
| 1933 |
作品《巴黎初春》、《法國莫列風景》が第七回台展で特選を受賞。 |
|
第十一回日本春陽展に入選。 |
|
| 1934 |
第十二回日本春陽展に入選。 |
|
|
李梅樹、陳澄波、廖繼春などの数人と「台陽美術協會」を設立。(此の協会は現在でも台湾芸術の主流として活躍中) |
|
呂鐵州、陳敬輝、曹秋圃たちと「六硯会」を結成。 |
|
| 1935 |
第十三回日本春陽展に入選し、春陽会会員に推薦される。 |
|
| 1962 |
国立芸術専門学校と私立中国文化学院(現文化大学)で教壇に立つ。 |
| 1986 |
第十一回国家文芸賞特別貢献賞を受賞。 |
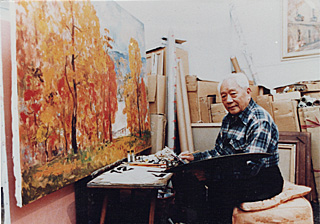 |
| 1991 |
「楊三郎美術館」を設立。 |
| 1992 |
台湾国家文化勲章を受賞。 |
| 1995 |
大統領表彰 華夏一等賞を受賞。 |
|
享年88歳で逝去。 |
|
民間人として初めて国葬される。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|